|
筆者は現在茨木市在住です。地理的に可能な方でご希望があれば手助けします。
学校の教科の中で、体育だけが苦手という人がいるように、音楽だけが苦手、という人がいますね。音楽の出来に男女差はあるのでしょうか?
お任せ下さい。、
笛、歌、ピアニカ、中間・期末テスト、実音テスト
音楽理論
楽譜の読み方。
夏休み等の宿題の作曲
バンドでのコード、聴音
小学校の音楽クラブ
音楽会対策。
教員志望の方で、音楽が苦手だけれど、音楽が必要な方。高三で初めてピアノを習う、という方
おおすみ かおり
連絡先 大墨 薫
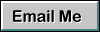
一般に男子学生は、音楽が苦手な人が多いかもしれないでしょう。しかし、それは、ピアノが弾ける人が有利な立場になりがちだからではないでしょうか。ピアノは女子の習い事の定番。しかし、男子にはそれほど必要が無いと考えられていたからでしょう。しかし、guitarやbase、drumsが弾ける男子は多いのではないでしょうか。ですから、学校生活や音楽の授業でguitarやbase、drumsを演奏・発表する場があればよいと思います。
音楽会-多人数の中に溶け込む? それとも果敢にリズム楽器に挑戦するか?
小学校の音楽会では、器楽合奏がありますね。演奏が得意でないと思う人は、リコーダー、鍵盤ハーモニカを担当しましょう。うまい人に助けてもらいましょう。
動きの少ない低音部を担当するか、高音部のmelodyを担当するかは、それぞれ好きな方を選びましょう。
逆に、自信のある人や注目を浴びたいという方は、パーカッション、木琴、鉄琴、piano、アコーディオンなどを担当しましょう。人数の多いpartに入って目立たない方がよい、という考え方もありますが、リズム楽器に挑戦することもお勧めします。タンブリン、カスタネット、すず、トライアングル、wood ブロックなどです。一見誰でもできそうですが、リズムの正確さを求められます。そして、注目されやすいpartです。リズム楽器に挑戦するのはどうでしょう。
パーカッションの中では、大太鼓は取り組みやすいです。たいてい1拍目と3拍目だけを叩く(one two one twoと言いながら)か、4分音符を4つ叩くことが多いです。もしくは、"だーいすき"のリズムを繰り返すなど、です。ですから勇気を持って大太鼓を演奏しましょう。
これが、小太鼓やタンブリンは、裏拍を演奏するので難しくなります。
最近の音楽会を見ると、パーカッションは男子ばかり。ピアニカを上手に弾く男子もたくさん。
むしろ筆者の方が、パーカッション(特に裏拍)は苦手。これまでかかわってこなかったpartです。
子どもの音楽会をvideoにそっと取りたい方、ペン型ビデオカメラがあります。
大学で初めてオーケストラ部に入ろう、という人。受験勉強が終わって、初めてクラブ活動で頑張ろう、オーケストラ部に入ろう、という人。
しかし、… 既に中学からブラバンに入っていた人や、子どもの頃から弦楽器をしていた人など、先役は少なくありません。大学生になって初めて楽器を始める人は、たいていsecond violinに入ります。2nd violinは、初心者と、それをcoverする一部の上級生で構成されます。その上級生は、理系などで、授業が忙しいために、負担の少ない2nd violinを担当する場合があります。あるいは、体が大きければ、チェロのように、低音部で音の動きの少ない楽器を選ぶのもよいです。大人になってから初めてチェロを始める人もいます。
小学校の音楽会 今昔
学校にもよるでしょうが、昭和40年代の音楽会は、教科書の文部省唱歌を歌ったり、演奏することが多かったと思います。器楽合奏では、marchが主か、リズムも難しくないクラシック系のものが多かったように思います。あるいは、音楽の教科書自体が、文部省唱歌が中心だったと思います。当時は、標準服(制服ではない)を着用し、全員が紺色の標準服を着て、壇上に立ちました。他にPTAのコーラス、音楽部の歌がありました。
中学の文化祭では、職員合唱があり、職員が一斉に壇上に並ぶと、生徒たちの冷やかしの声が上がりました。
今でも、小学校の音楽部は男子は少ないものでしょうか。昭和40年代の音楽会では、男子は3人以下、全くいない場合もありました。3人しかいない男子が、壇上の中央に上中下、と制服のボタンのように並んだのも見ました。そして、歌が"荒城の月"。たとえ3人でも、この学校は、男の子もいて、感心だ、とも言われました。(そう、筆者が小三まで在籍し、転校後に訪れた安井小学校)
筆者自身は、そのような昔の音楽会や授業、あるいは小学校自体が少しも嫌いではありませんでした。ほほえましく思います。
現代では、showの要素が多くなり、costumeもそろえ、danceも取り入れたりしています。選曲もTVの主題歌、他、軽音楽が多くなりました。中には創作音楽もあります。例えば、"雨"をテーマにした音楽を発表するなど。楽器も手作りです。
昔の文部省唱歌が、今の時代に合わなくなったものもあり、教科書から削除されたものもありますが、逆に、昔の唱歌を味わおう、という中高年向きの講座もありますね。
ペン型ビデオカメラ
最近の小学校では、音楽会でも、参観日でも撮影を禁止されています。児童の委員が見回っているほどです。
音楽会では、専門の業者が写真撮影をし、後に注文する仕組みになっています。
でも、どうしても自分の子どもの写真を撮りたい、というなら、ペン型ビデオカメラがあります。見た目は目立たない黒いボールペンです。
http://www.kididdles.com/ |


![]()
![[stmx] - ソーシャルマーケットプレイス](http://sun.d-064.com/han/images/banner_program/sp-gakki_120-60.jpg)


